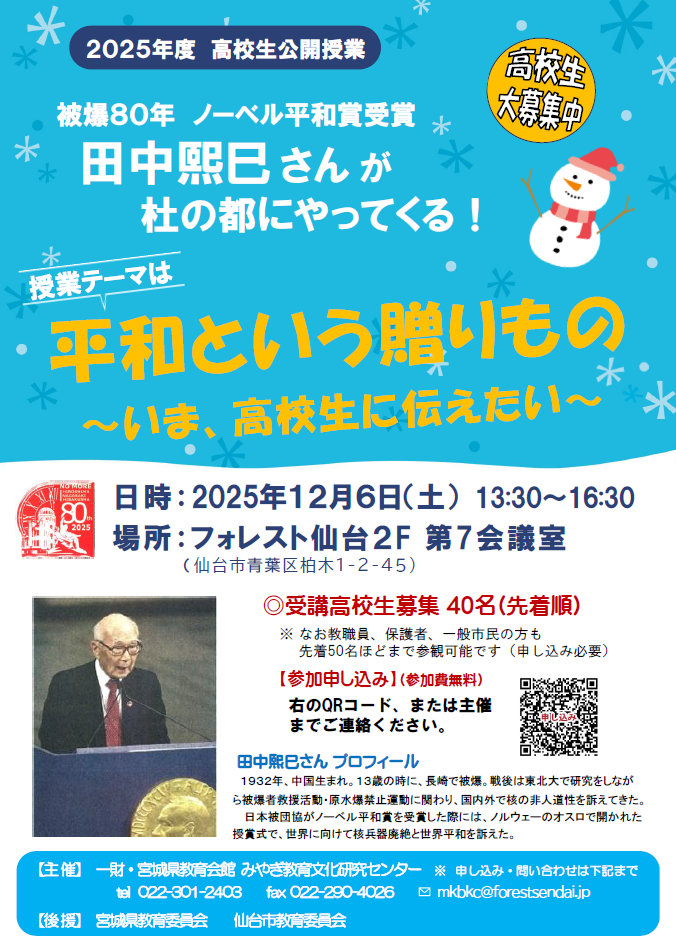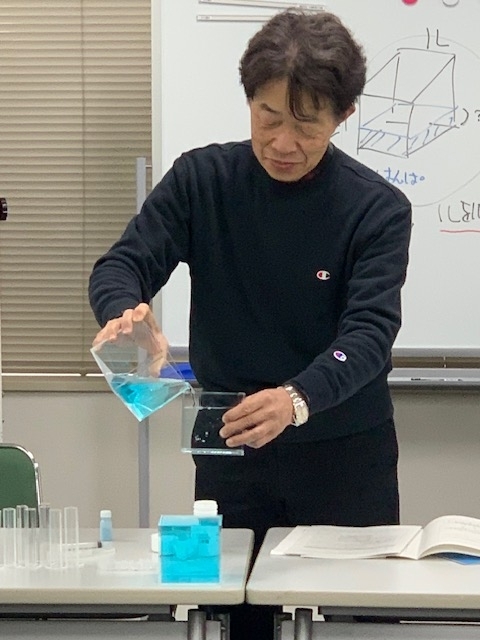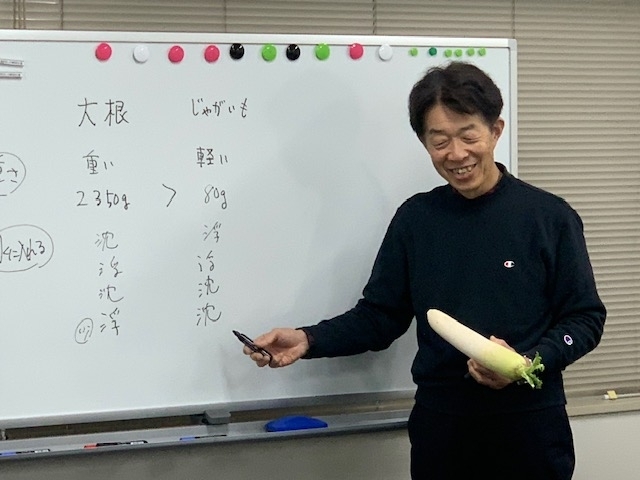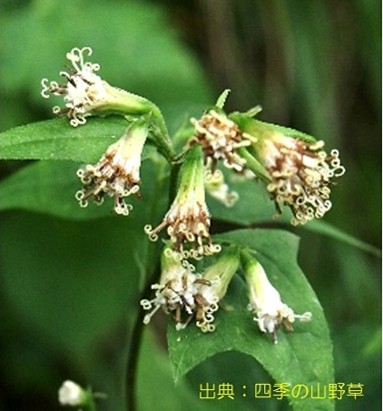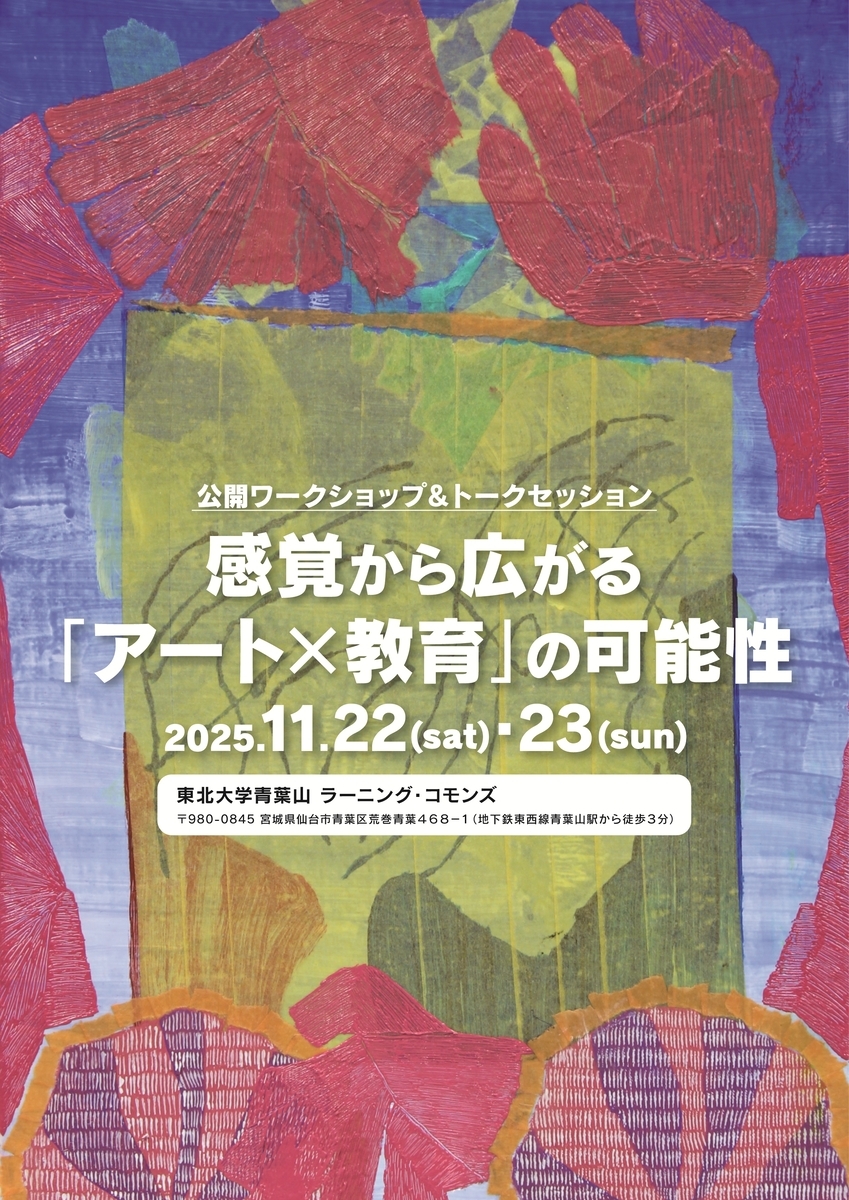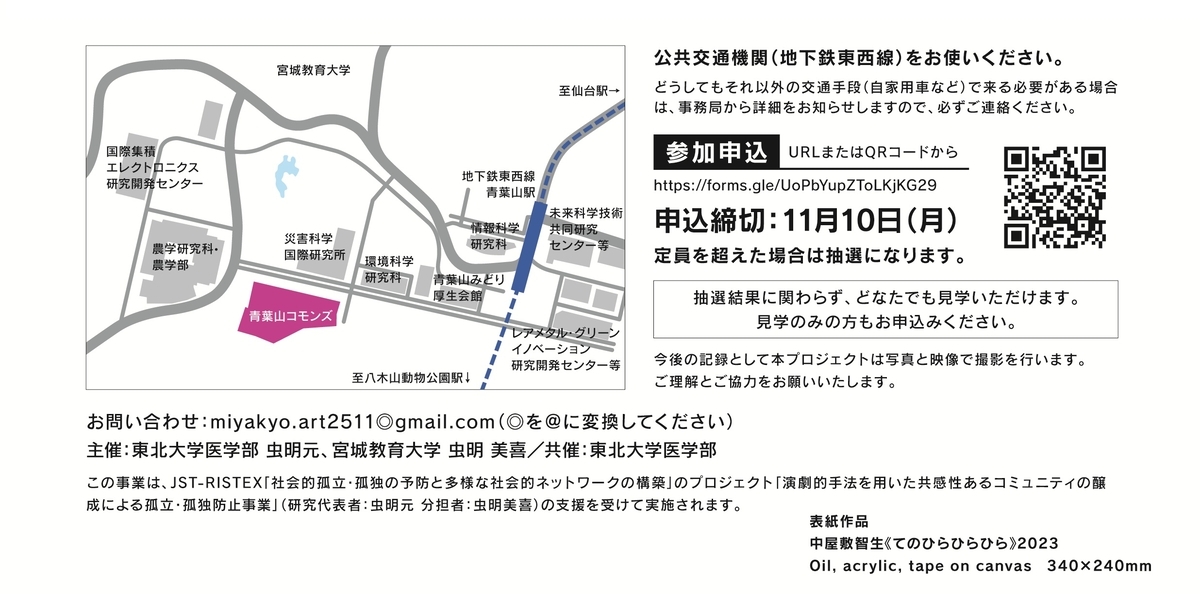6月10日(水)快晴
〈スカンディナビア旅行 ⑤ スカンディナビア半島横断〉
今日も澄みきった真っ青な空が広がっている。ウプサラから海沿いにSundsvollまで北上する。約300kmの行程である。交通量は多く、トラックが次々と追い越していく。海岸沿いには小さな町が点々と並んでいる。真夏のように暑い。もう北欧の短い夏のまっただ中なのであろう。Sundsvollから左に折れて、スカンディナビア半島を横断する道路に入る。湖沼と森林がどこまでも続く500km近くの行程である。しばらくは残っていた街の気配も次第に消えて、道は樹林帯の中に入っていく。残念ながらここでも伐採が進んでおり、広大な面積が無残にも切り拓かれている。スウェーデンでも伐採による原生林破壊が相当進んでいるのである。ニルス君が言っていたように、スウェーデンの最大の産業は林業なのだ。
右に左に次々と湖が現われ、真っ青な水面が目の前にぱっと広がる。氷河によって削られてできた湖で、フィンランドとスウェーデンにはこのような大小の湖沼が数限りなくある。スウェーデンで 約10万近く、フィンランドで約5万の湖があるそうだ。湖水面積はフィンランドの方が広く、国土の半分は湖ではないかと思われるほどである。湖水の周りには針葉樹の原生林、どの湖も手付かずの自然のままで、絵のようであり、水は澄みきっている。ここでは湖の間を縫ってのドライブが思う存分堪能できるのである。
Ostersundまでやってきたときにはもう夕刻であった。600kmほども走ったことになる。街を散策して、湖畔の草地に車を寄せる。雛が4匹の鴨の一家が草の上で休んでいたが、車に驚いて湖を泳いで逃げていった。寝場所を奪ったおわびにパンくずを草の間に投げておいた。都会ではユースホステル、自然の中では車中泊の旅行である。前席が倒れてフラットになるのである。湖畔の野宿は最高の気分だ。12時を過ぎてもまだ空は明るく、深夜でも暗闇にならない。夏至がもう間近なのだ。あと500kmも北上すれば白夜の世界であるが、今回はあいにくと日数が足りず断念。
6月11日(木)快晴
〈スカンジナビア旅行 ⑥ ノルウェーへ〉
Ostersundからノルウェー国境までは180kmの行程である。周りの風景が一段と高原の様相となり、針葉樹林と小さな湖沼、水量がたっぷりの急流、そして遠くには残雪に輝く山々。山容はゆるやかであり、広大な裾野がそのまま大平原となって、地平線に消えていく。しかしなお国道の両側には伐採箇所が多く、山肌にも無残に刈り払われた跡があちこちに見られ、心を突きさす。標高を次第に上げて国境に到着。両国のそれぞれの側にレストランが一軒づつぽつりと建っていた。
ノルウェーに入ると風景は一変する。なだらかな高原状の大地はもはや見られなくなり、国道は急峻な谷あいを急なカーブを描きながらどんどん下っていく。山が険しくなると、むしろ日本の山岳地帯にそっくりの風景になる。道路は狭く、谷にへばりつくように民家が散在している。100km余りで道はフィヨルドの海岸に沿って走るようになり、ほどなくトロンハイムTrondheimの街についた。ノルウェーで3番目に大きな都市である。とはいっても、人口は13万人余にすぎない。それほど広くない都心は、短かい夏を楽しむ人たちでいっぱいである。この街にもまた美しいDOMがある。巨大な石像の建物で、二つの重厚な尖塔をもつ。北欧の建物はほとんどがレンガ造りであり、ウプサラのDOMも明るいレンガ造りであったが、ここのDOMは石造である。正面のファサードは3層にわたって聖像彫刻が列をなし、午後の日差しを浴びて燦然と輝いている。いかにも極北の面影のある(?)大聖堂の下で、しばしカトリック世界の深みに浸る。
街を散策した後、フィヨルド寄りの地方道を楽しもうと、海辺の道に出た。ところが、30分ほども走ると車が不調を訴え始めた。ノッキングとエンストを繰り返し、トップギアが入らなくなった。立往生する前に修理をしなければならない。急遽、コースを国道に替えて、セカンドギアにシフトダウンし、エンストを起こさないように20〜30km/hの超低速で走り、ようやく20km余り先のところで修理工場のあるガソリンスタンドにたどり着いた。その間2時間余りのひやひや運転だった。応急の点検をしてもらったが、エアフィルターの下の部分Carborater(キャブレター)の本格修理が必要らしく、明日修理をしてくれることになった。老朽車を長旅させたので疲れが出たのであろう。ウプサラを越えたあたりから不調を感じていたが、山間部をさんざん走らせたものだから、音を上げたのであろうか。
近くの宿を紹介してもらって、思わぬ宿泊となった。
6月12日(金)快晴
〈スカンジナビア旅行 ⑦ノルウェーの自然景観 〉
午前中は車の修理。キャブレター(ガソリンに圧縮空気を送り込み気化させる装置)の目詰まりらしく、丹念にオーバーホールしてもらった。元気になった車を走らせて、ここからソグネフィヨルドへと向かう。
ノルウェーの中央高地というべきオプダルOppdal地方は夢のように美しい高原の世界である。豊富な残雪が残る山々は標高が1600mから1800mであり、最高峰のSuφheltは2286mの高峰である。 先の尖った鋭いピークと純白の稜線、そして刷毛で描いたような美しい裾野が目の前に広がる。U字渓谷特有の地形であり、その美しさに身も心も奪われる。ノルウェーは山国であり、1000mから2400mの山々が細長い国の脊梁を形成している。ソグネフィヨルドのあたりが一番標高が高く、北に行くほど標高が下がっていく。
OppdalからDombasへと抜ける国道E6は、U字渓谷の底をゆるやかなカーブを描きながら走り、道の両側には湿原状の原野、池塘、湖、堆石、清流が次々と展開して、すばらしい高原景観がどこまでも続く夢のような道路である。カーブを曲がるたびに新しい景色が目に飛び込んでくる。車を何度も止め、岩に腰をかけ、流れに手を浸してみたりする。1本の道路と、時々現れるヒュッテ風のホテル以外には人工的なものは何もない。車で走り抜けてしまうのが惜しく、このようなところで何日も過ごせたらと思う。
雲ノ平や朝日連峰、大雪山系の自然景観は言葉に表しようのない美しさであるが、Oppdalの景観はやや荒削りであるが、はるかに雄大である。花はほとんど見られず、季節がまだ早いのかもしれない。山々はどこまでも端正であり、空気は張りつめ、水は豊かに流れ、澄みきっている。このような景観がどこまでも続く。ようやく道が谷あいを降り始め、下りきったところにある小さな町Dombasに着く。この町はフィヨルドやOppdalへの中継点らしく、観光客でいっぱいである。ここから数十キロほど川に沿ってOttaの町までいったん下り、そこから右折して川沿いの急な登り道を、Krossbu峠へと向かう。
ノルウェーの川は、どこでも溢れるほどの豊かな水量の流れが勢いよく谿を駆け下る。雪解けの季節なのであろう。われわれは普段水量の貧弱な川しか見なれていないから、道路の近くまで清流が激しく流れているのを見ると迫力を感じ、これが川というものかと思ったりする。日本は川の国であるのに、その多くが伐採で水源を奪われ、ダムで水をとられて、かろうじて細々と流れを保っている。木曽川も大井川も黒部川も滔々とした流れの時代はとうに過ぎ去っている。道路が俄然急になり、どんどん標高を上げていく。ソグネフィヨルドの源頭部、2000mから2400mの高峰が並ぶ地域に向かうのである。狭く急な峠道を登りつめていくにしたがって、道路のそばまで残雪が現れるようになり、峠付近では雪の壁になってしまった。Krossbu峠は標高1400m、周囲は一面の銀世界であり、冬のままの景色である。山々は鋭い岩峰と岩壁で、カールや氷河を抱くその山容はスイス・アルプスに劣らない雄大さであり、人を寄せつけない厳しい姿で林立している。
ノルウェーの山々は標高が2000メートル台のためであろうか、あまり知られていない。最高峰は標高2469mのGaldhφppingenであり、ソグネフィヨルド源頭部には2000mを越える山が10座以上ある。それぞれが個性的な形をした岩峰であり、岩の黒と雪の白とが強いコントラストをなしている。これらの山々から氷河が一気に海に流れ落ち、深いフィヨルドをつくるのである。フィヨルドは氷河をもつ高い山々があって初めてできる。山が高ければ高いほどフィヨルドは深くなる。フィヨルドの両岸はU字状の断崖であり、海面から真っ直ぐにせり上がった断崖は千数百メートルに及ぶことがあるのである。圧倒的な山岳景観であり、そして谷の底は陸地奥深くまで切り分けて侵入する入江の海である。海から見れば、頭上の岩峰から何本もの滝が落ちてくるのが望め、山の上から見れば、足元の眼下は黒い水を湛えるフィヨルドの海面である。
フィヨルドは同時に険しい山岳地帯であるから、陸上交通は不便を極める。人々はフィヨルドの谷底にひっそりと暮らしている。ソグネフィヨルドは外海から200kmも山岳地帯を内陸に向かって延びている。その狭い海沿いに小さな集落が点々と散在するのである。昔は海が唯一の交通手段だったであろうが、崖の下の猫の額ほどの土地に外から隔絶されて何百千年も生きてきたのである。生きることの意味を考えさせられるほどの地形である。
峠からは、1400mの標高差を海まで一気に下る。ヘアピンカーブを繰り返しているとほどなく海面に降り立つ。ソグネフィヨルドの一番奥の入江である。山から海へあまりにあっけなく降りてしまったので、はじめは途中に湖でもあったのかと錯覚したほどである。フィヨルドだから海とはいっても周りは全部山であり、湖のように見えるのである。海であることを確かめるために海水をなめてみたら薄塩の味であった。流入する川の水のためにほとんど真水に近いのである。
フィヨルドに沿って100kmほど外海のほうに向かう。小さなフィヨルドがいくつも枝状に入り込んでおり、そのたびに道は大きく迂回しなければならない。Hellaからフェリーに乗って対岸のDragsvikに渡る。フィヨルドの中は何種類ものフェリーが常時運行しているのである。Melまで枝フィヨルドを奥に進み、そこから再び標高750mの展望台まで登った。
6月13日(土)快晴
〈スカンジナビア旅行 ⑧オスロへ 〉
展望台から北上し、湖(フィヨルドになりきれなかったU字渓谷の一部で、必ず細長い)に立ち寄る。峠に着くと周りは再び銀世界、湖はまだ水面が雪で覆われている。湖畔の村でUターン、のびやかな下り道の途中で何回か羊の群れに出会う。道路をゆうゆうと歩いている。夏の間放牧されるのだろうが、峠の付近まで上がってきており、野生の羊に出会ったような感じだ。はじめは羊も警戒していたが、ビスケットをあげていると、子羊連れが10頭以上も集まってきて、全部食べられてしまった。この羊がノルウェー製のソックスやセーターになる。私は山のソックスはノルウェー製を愛用している。雪の中を平気で歩き回っているのだから暖かいわけだ。
再びフィヨルドをフェリーで渡ってVangsnesへ。ここからまた標高1000mの峠まで猛烈な登りを繰り返す。登りきればまたまた銀世界、再び急な下りで隣のフィヨルドへ。ソグネフィヨルドの長い枝フィヨルドである。
Fråmの入江を最後にオスロ方面の道に入る。途中の民家が印象的である。ノルウェーは平地がほとんどないから、山の斜面を切り拓いて村が作られている。スウェーデンの民家はログハウスを赤っぽいチョコレート色に塗り、四すみの窓を白く塗った家が一般的だが、ノルウェーの民家は厚い板張りを黒の防腐剤カラーで塗り、家の形も思い思いにさまざまなのが特徴的だ。ときどき「草屋根」の家を見かける。勾配をなだらかにし、そこに土を盛り、本当に芝のような草を植えるのである。草の音が張っているので土は流れない。「庭のような屋根」だから雰囲気はよいが、どのようなメリットがあるのだろうか。冬暖かいのかもしれない。
夕方の雑踏のなか、オスロに着いた。
6月14日(日)晴れのち曇り
〈スカンジナビア旅行 ⑨オスロから帰路を急ぐ 〉
今日はもう日曜日、明日の午前中にケルンに帰らなければならない。旅の日程は1日予定より遅れている。オスロからケルンまでは1300km、仙台からはほぼ下関辺りまでの距離である。
オスロOsloでもゆっくりしたかったが、急がなければならない。オスロの中心街は意外に小さい。駅と王宮とを結ぶカール・ヨハン通りがオスロの目抜き通りである。駅はモダンな最新の建物で、ゆったりしている。駅の目の前にオスロのDOMがあるが、それほど大きくもなく、個性的でもなく、普通のカテドラルである。通りに面して国会議事堂、オスロ大学講堂(アウラ)、国立劇場などがある。王宮の正面まで行って、Uターンして駅に戻る。ムンク美術館などは省略。
オスロから約1時間で国境を越え、再びスウェーデンに入る。さらに2時間南下してヨーテボリGötebergに着いた。ヨーテボリはスウェーデンでは2番目に大きな都市である。駅前に車を置き、昼食を兼ねて市内を散策する。港町であり、旧市街は駅から港にかけて広がっている。大きなショッピングセンター、市庁舎、グスタフ・アドルフ広場を通って、港を観に行った。港にはひときわ大きな帆船が係留されており、小さな漁船がひしめくように並んでいて活気に溢れている。埠頭には17、8世紀のものと思われるレンガ造りの大きな倉庫が2棟並んでいた。ヨーテボリからさらに2時間南下してヘルシンボリに戻ってきた。ヘルシンボリも古い街だが、そのままフェリーに乗り込んで、デンマークに急ぐ。どうしても観ておきたい所が2箇所あるのだ。
デンマーク側のヘルシンゲアにはクロンボー城Kronborgがある。『ハムレット』の舞台になった城である。15世紀の古城で、ロの字型の古風な造りである。『ハムレット』の冒頭に出てくる、王の幻が出たという夜衛の塔は右手奥に見える塔のことだろうか。シェイクスピアは実際にこの城を訪れたのであろうか。『ハムレット』に描かれる城と実際のクロンボー城とは一脈通じるところがあるようなないような難しいところだ。4時半過ぎに城に入ったのに、建物の内部見学を認めてくれない(入館は5時まで)。30分足らずでは内部を観て周れないと言うのである。せっかく来たのだからと2回頼んだが、頑としてはねつけられた。私の後からも観光客が次々と入ってくるというのに。駄目なら入館は4時半までと書いておくべきである。少し頭にカチンときて、ハムレットのように城内ならぬ中庭をぐるぐると歩きまわった。
ヘルシンゲアから田舎道を北に向かって、ギーレライエGillelejeを訪れる。ギーレライエはシェラン島の北の端にある岬である。断崖(といっても実際には30m程度のゆるやかな崖)になっており、北海を隔ててスウェーデンが見渡せる。ギーレライエはまだコペンハーゲン大学の学生であったキルケゴールが夏の一日ここを訪れ、手記をしたためた所である。この手記は今日「実存宣言」とも呼ばれ、実存主義の発端となったものである。「私にとって真理であるような真理を発見し、私がそれのために生き、それのために死にたいと思うイデーを発見することが必要なのだ」。
若いキルケゴールが「実存Existenz」に行き着いたその場所を訪れることは長い間の私の夢であった。夢は大抵裏切られるものだが、「断崖」は思っていたよりかなり低く(デンマークに高い断崖のあるはずがない)、「人家の途絶えた 荒涼たるヒースの原野」は岬のすぐ近くまで瀟洒な家の立ち並ぶ遊歩道であった。ギーレライエは静かで落ち着いた街である。家々は海岸沿いにまで並び、どの家も広い庭をもつ立派な建物である。キルケゴールの記念碑を案内する表示は何一つなく、通りにも人影はない。海岸に沿って行けばそのうち行き着くだろうと思い歩き出す。住宅の庭の茂みとハマナスの茂みとの間の散歩道は趣があって美しい。海を見ながら、このようなところに住めればすばらしいことだろうと少し羨望心を持ちながら歩くが、なかなか見つからない。はまなすをそのまま自分の庭に取り込んで花を楽しんでいる家、藁葺き屋根の立派な家、素朴な丸太のフェンスを過ぎ、庭木の手入れをしている人を見つけ、場所を訊いた。記念碑は松林の中にひっそりと立っていた。海が開けて見え、なかなかよいところだ。キルケゴールのように何かひらめいて来ないかと思って、半時間余り崖っぷちに腰を下ろしぼんやりと海を眺める。何の「イデー」も湧かないまま、断崖を離れ、車まで戻った。
ギーレライエからは寄り道もせず、ケルンに向かってひたすら走る。約800kmの行程である。ハンブルクに着いた時は夜中の1時過ぎ、いつの間にか都心に向かうアウトバーンを走っていて、あわてて引き返す。近くのサービスエリアで停泊。
6月15日(月)曇り
〈授業に出席 〉
ハンブルクからケルンまでは400km。少し寝過ごしてしまったので、急いで朝食をつめ込み、ケルンまでノンストップで飛ばす。そのまま大学へと向かい、駐車場に車をつけたのが12時45分、授業の始まる定刻である。我ながら無茶なことをしたものだ。別にさぼっても支障はないのだが、このようなときに限って真面目に出たくなる性分である。今回の旅行の走行距離は5001km、ずいぶんと車を酷使したものだ。ウプサラの大聖堂とノルウェーの大自然とがよかった。テキストもノートも持たずに授業に出る。疲労感に襲われて夢うつつの授業であった。
(太田直道)